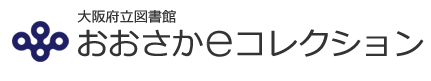本資料のURL
横並び
二次利用条件
| 資料ID | 02-0000149 |
|---|---|
| 作品名漢字 | 難波橋の風景 |
| 作品名読み | ナニワバシノフウケイ |
| シリーズ名 | 浪花十二景之内 |
| 画家名漢字 | 貞信(二代)画 |
| 画家統一名 | 貞信(二代) |
| 画家統一名読み | サダノブニダイ |
| 画家解説 | 貞信(二代、初代小信) さだのぶ(このぶ) 嘉永元年(1848)~昭和15年(1940) 長谷川氏。初代貞信の長男。通称徳太郎。はじめは小信と称したが、明治8年(1875)父貞信の跡を襲い二代貞信と称した。父貞信(初代)の下に修行していたが、のち一鶯斎芳梅に学んだ。慶応3年(1867)20才頃から画作をはじめ、鳥羽伏見の戦い、続く明治天皇の難波御幸など当時の世情を主題にした作品を一挙に描いた。維新以後も、大阪市中の開化風俗を描く錦絵・風景版画を数多く遺した。 その他、錦絵新聞や新聞小説の挿絵、芝居絵や肉筆風俗画も手がけた。 |
| 請求記号 | 甲雑/32/# |
| 名所名1 | 難波橋 |
| 名所名1読み | ナニワバシ |
| 現在の市区町村1 | 北区 |
| 現在の市区町村2 | 中央区 |
| ジャンル名1 | 橋 |
| ジャンル名2 | 水上交通 |
| 作品解説 | 現在は堂島川、中之島公園、土佐堀川にまたがって架かり、ライオン像を有することで知られている。架橋年代については豊臣時代に架橋されたのではないかといわれているが、『元亨釈書』に天平17年(745)僧行基が摂州に難波橋を架けたという記事もあり、正確なところは定かではない。 江戸期には浪華三大橋として公儀橋に指定され、界隈には諸藩の蔵屋敷が建ち並びそれを取り巻くように問屋街が形成され、西鶴の『日本永代蔵』にも「難波橋より西見渡しの百景、数千軒の問丸、甍をならべ、白土雪の曙をうばう。杉ばへの俵物山もさながら動きて、人馬に付おくれば、大道轟き地雷のごとし。上荷、茶船かぎりもなく川浪に浮かびしは、秋の柳にことならず。」とあるように大変な賑いをみせた。また納涼や花火見物、花見、月見にも絶好であったという。 |