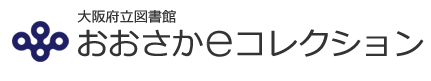本資料のURL
横並び
二次利用条件
| 資料ID | 02-0000148 |
|---|---|
| 作品名漢字 | 心斎橋 |
| 作品名読み | シンサイバシ |
| シリーズ名 | 浪花十二景之内 |
| 画家名漢字 | 小信画 |
| 画家統一名 | 貞信(二代) |
| 画家統一名読み | サダノブニダイ |
| 画家解説 | 貞信(二代、初代小信) さだのぶ(このぶ) 嘉永元年(1848)~昭和15年(1940) 長谷川氏。初代貞信の長男。通称徳太郎。はじめは小信と称したが、明治8年(1875)父貞信の跡を襲い二代貞信と称した。父貞信(初代)の下に修行していたが、のち一鶯斎芳梅に学んだ。慶応3年(1867)20才頃から画作をはじめ、鳥羽伏見の戦い、続く明治天皇の難波御幸など当時の世情を主題にした作品を一挙に描いた。維新以後も、大阪市中の開化風俗を描く錦絵・風景版画を数多く遺した。 その他、錦絵新聞や新聞小説の挿絵、芝居絵や肉筆風俗画も手がけた。 |
| 請求記号 | 甲雑/32/# |
| 名所名1 | 心斎橋 |
| 名所名1読み | シンサイバシ |
| 現在の市区町村1 | 中央区 |
| ジャンル名1 | 橋 |
| ジャンル名2 | 文明開化 |
| 作品解説 | その名は、江戸初期の長堀川開削に功績のあった岡田(美濃屋)心斎が、私費で架けた橋であることに由来する。 江戸の末頃には吊り橋となっていたのを、明治6年(1873)に工事費1万9千円という高価なドイツ製の吊鉄橋に変え、当時の人を驚かせたという。ちなみに、現在この橋は鶴見区の鶴見緑地内に保存されている。 ただし、この鉄橋は幅が狭いなどの不便があったため、明治42年(1907)にまず小西荘次郎という者が手掛け、その後を大阪府が引き継ぐ形で4代目の心斎橋が誕生した。夕暮れには欄干に立てられたガス燈が点る、市内で最も美しい橋とされていた。 長堀川が昭和39年(1964)に埋め立てられると、もとの心斎橋の辺りは横断歩道が交差するようになり、今では「心斎橋跡」と刻まれたフラワーポットが置かれている。 |